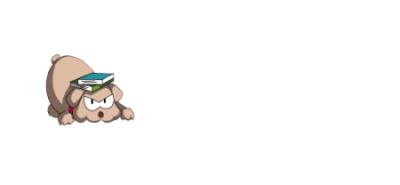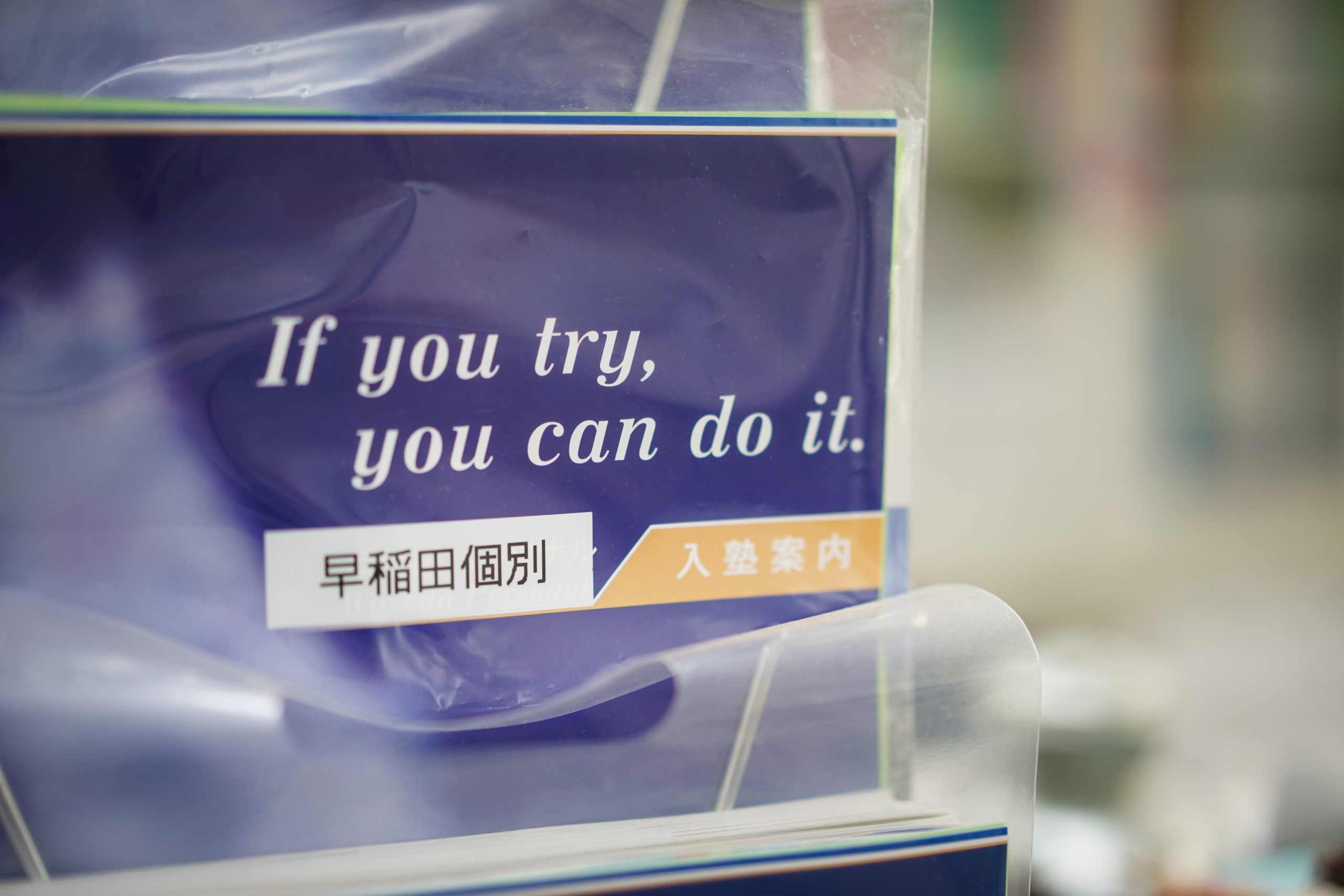文部科学省教員メンタル対策手引き作成へ
精神疾患で休職する公立小中学校の教員が増加する中で、文部科学省は今年度、復職支援や学校現場でのメンタルヘルス対策に関する手引きを作成すると発表した。休職者の増加は教員不足の大きな要因の一つとなっており、医師や心理士の専門の知見を取り入れた対応策を示すことで改善を図るとしている。
手引きは全国の教職員らが加入する公立学校共済組合に委託して作成する。具体的には、
1.医療機関と連携した「復職支援プログラム」作成のガイドライン
2.休職中の過ごし方のポイント
3.部下への対応策
以上の3点がポイントとなるようだ。
作成にあたり組合は、早期復職や精神疾患の再発防止につながる支援方法を分析する。その上で組合が運営する三つの病院で教育委員会と共に効果的な復職支援策などを探るとしている。
管理職向けの手引きの作成では、組合が運営する病院が中心となって小中学校の校長らを対象にアンケート調査などを実施予定としている。管理職が部下のメンタル不調を防いだり職場環境を改善したりする方法を検証して手引きに盛り込む予定だ。
精神的に追い込まれて休職する教員は近年、毎年のように増加している。文部科学省によると2023年に精神疾患で休職した公立学校の教員数は7119人で、3年連続で過去の最多を更新した。休職の原因は児童生徒に対する指導や職場の対人関係が目立った。また保護者の過度な要求や苦情への対応に疲弊する教員も少なくはない。休職者の増加は前述したように教員不足の一端を担っており、全国公立学校教頭会の調査では、昨年度当初に小中学校の2割で教員の欠員があった。
就職を控える大学生においては、教員は「ブラック」というイメージが払拭されておらず、それは教員採用試験の倍率からも裏付けられる。働き方改革によって部活動指導を外部委託にするなど改善はされているもののまだまだ不十分であり、一般企業と比較した時にその差は大きいと判断できる。教員はやりがいがある、誇り高い職種である、といった精神論的なことを唱える時代とは程遠くなっていることを改めて噛みしめる必要があるのではないだろうか。