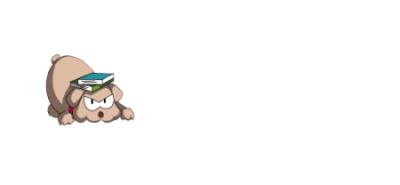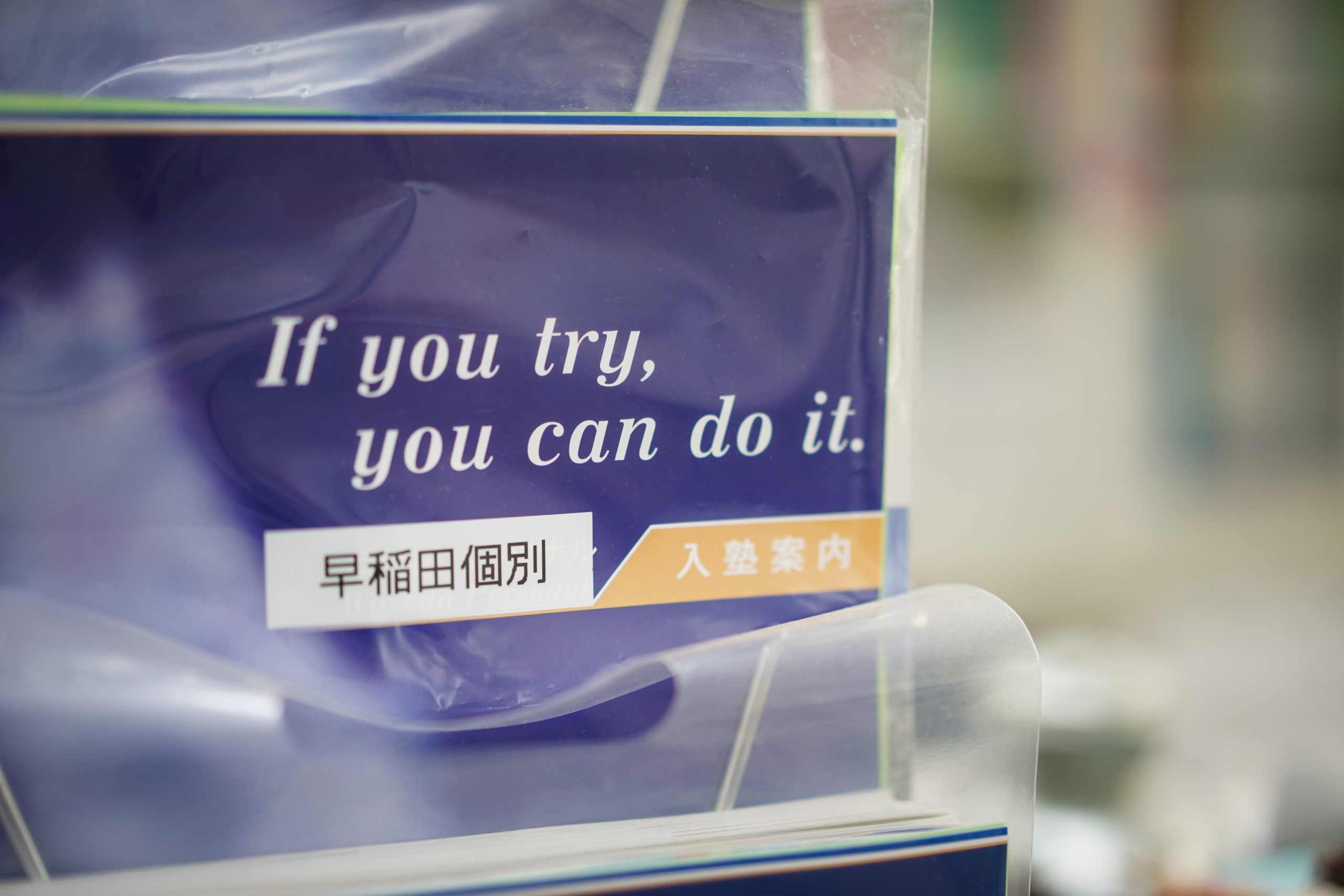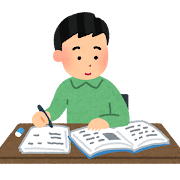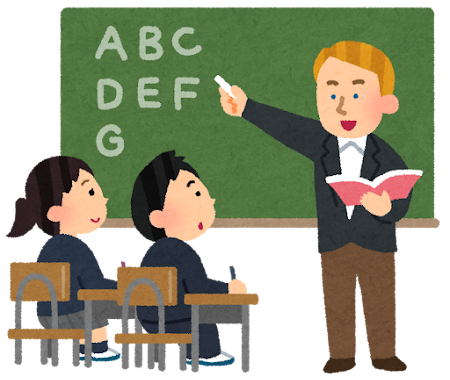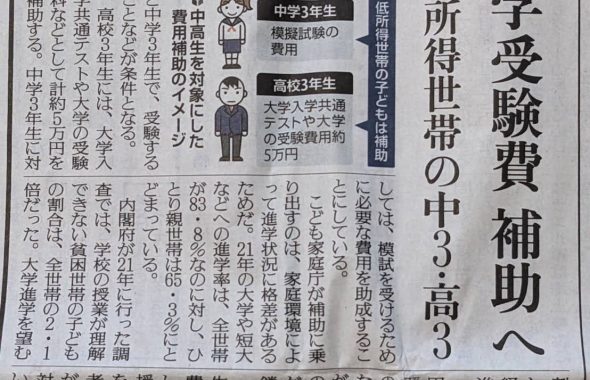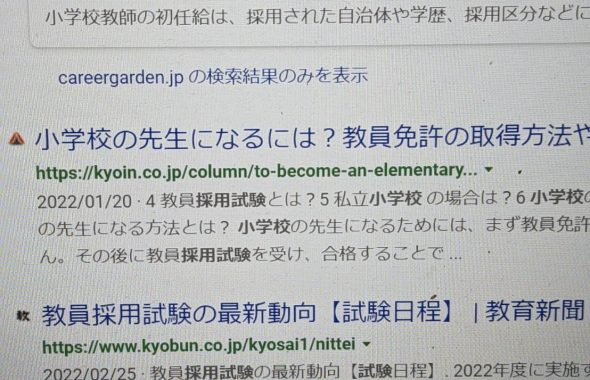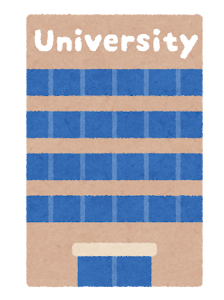
174経営難の私大・短大
私立大学や短期大学を経営する学校法人の4分の1にあたる174法人が、経営難に陥っていることが11日、日本私立学校振興・共済事業団の調査でわかった。このうち19法人は、自力再生が極めて困難な「レッドゾーン」に分類された。最近の物価高が拍車をかけたとみられる。
経営難と判断された学校法人数は、昨年の調査から38法人増え、過去最多となった。事業団は文部科学省が所轄し、私学助成金の分配や経営支援を担っている。大学・短大経営の撤退や他法人との合併、学部の譲渡などの対応を求めている。
この調査は大学や短期大学を経営する全国681の学校法人が対象で、各法人が2024年6月までにまとめた2023年度決算についてであり、教育に関連する収支が直近3年のうち2年以上赤字、負債が運用資産を超過している、といった項目8つの指標を用いて分析し、経営状況を4段階に分類した。その結果、2.9%にあたる19法人が、在学生が卒業するまでに経営破綻の恐れがあり、「自力再生が極めて困難」という状態であった。さらに23.4%にあたる155法人が「経営困難な状態」にあり、合計した174法人が経営難にあると判定された。また約4分の1以上となる27.5%の182法人は、経営指標に悪化の兆候が見られ、経営困難な状態の「予備的段階」とされた。
一方、46.1%にあたる305法人は「正常な状態」とされ、割合からも分かるように半数を初めて割り込んだ結果となった。
残念ながら経営難の学校法人の割合が増えたのは、少子化で学生募集が難しくなっていることに加え、光熱費の上昇で収支バランスが悪化したと分析できる。このような中最も懸念しているのは、在学生がいる間の経営破綻である。乱脈経営により資金繰りが悪化した群馬県の創造学園大学のケースは、文部科学省が2013年に学校法人の解散命令を出し、在学生150人の受け入れを各地の大学に要請するなど混乱を招いた例はまだ記憶に新しいところである。
また現在は大学・短期大学に注目が集まっているが、近いうちに高校においてもこの波は避けられないであろう。多くの学校が別学での経営は難しいと判断し、ここ港南中央教室近隣の私立高校でも、横浜高校や横浜富士見高校、そして鎌倉女子大付属高校の各学校の共学化がそれを示している。少子化の中、生き残ることは、そう簡単なことではないことが容易に想像できる。