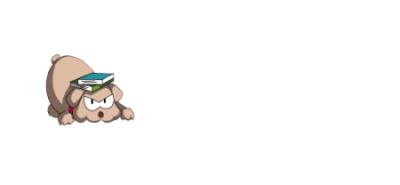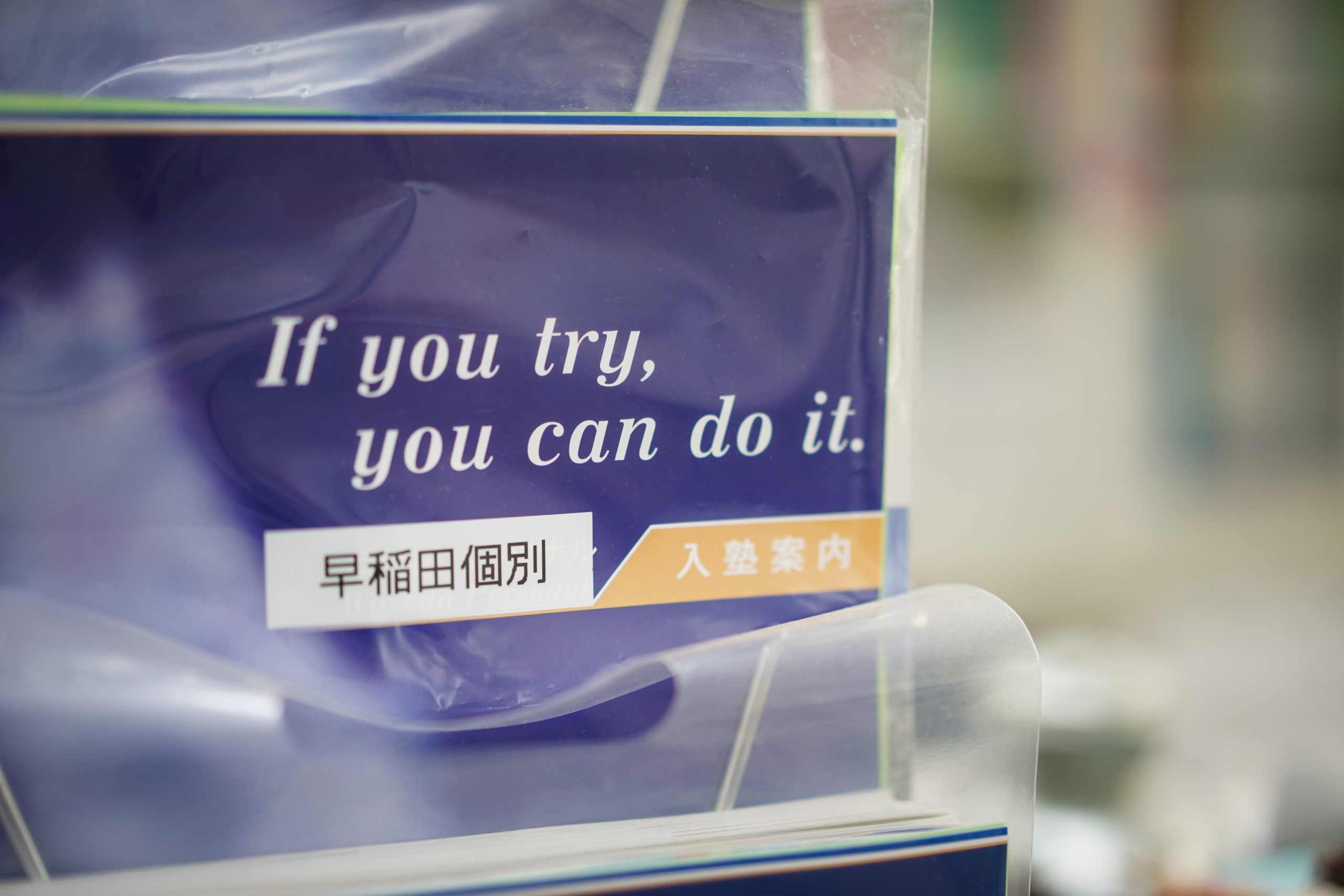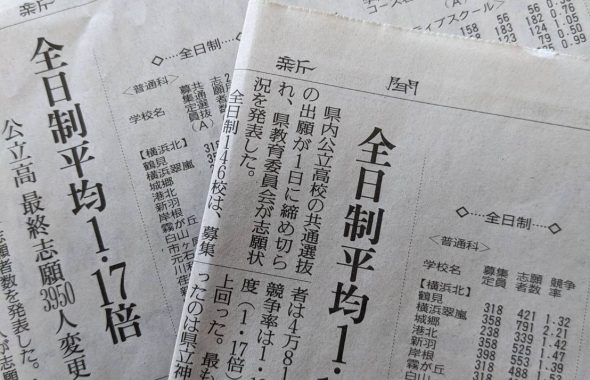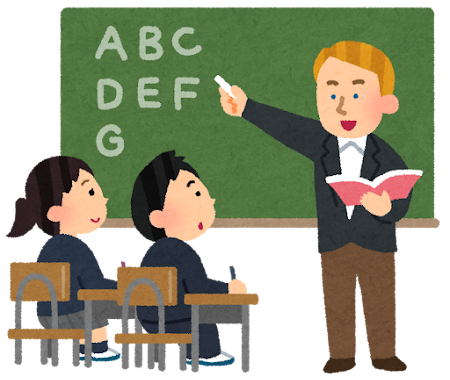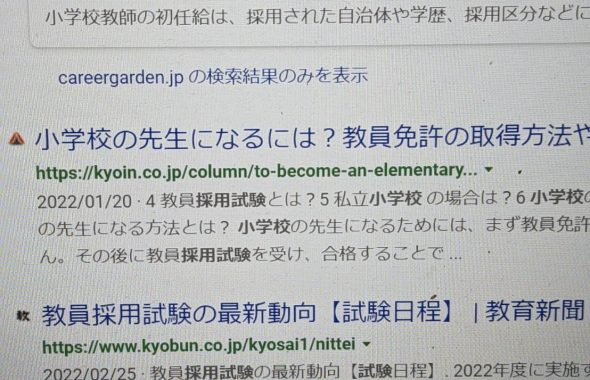教員採用試験5月実施は大半が見送り
教職員の成り手が不足する中、今年度の教員採用試験を5月に実施する教育委員会が、全国68都道府県・政令指定都市のうち10教育委員会に留まったことが新聞社の調べで明らかになった。
文部科学省は人材確保に向け、教員採用試験の早期化を各教育委員会に促し、5月11日を実施の目安としていたが、大半がこの前倒し日程を見送った。
教職員の採用試験は従来、7月に一次試験となる一般教養や専攻する教科知識・技能などの筆記試験が、8月に二次試験となる面接試験や実技試験が行われる。そして合否の発表は9月から10月に行われるのが一般的である。しかし民間企業の採用活動の早期化などを受け、文部科学省は昨年度6月10日に設定した。しかし今年度はさらに1か月ほど早めたのだが、前述したとおり、静岡県や長崎県、茨城県、新潟県、また静岡市や浜松市等といったわずか10教育委員会にとどまった。日程を早めたある教育委員会では、競争倍率が昨年1.7倍から2.0倍へと14年ぶりに上昇したと発表している。
民間企業の採用選考は6月1日に解禁されることから、「競合する民間の採用活動に対応した」と県の担当者の話もある。5月10日の採用試験日程ではなく、5月17日に教職員採用試験を実施するとした島根県でも、昨年度より出願者数が86人も増え応募者は1,182人となったことも注目するに値する。
しかし、これらの日程には一つ大きな問題があると考える。多くの学校で受け入れる教育実習日程は、5月から6月に行われていることだ。まず教職員採用試験の勉強の追い込みと時期と教育実習の教材研究などの準備が重なってしまうこと、そして最も問題視しなければならないのは、教育実習の手応えによって教員志望を確固たるものとして採用試験に臨めなくなることである。
このようなことからまた新たな問題も発生すると考えられるのではないだろうか。それは、1次試験が合格しても2次試験には進まず、採用試験を途中辞退する学生が多くなるのではということである。
これらを回避するためにも、働き方改革を明確化し、なり手の不安を解消すること。これが実現していかないことには、教職員の確実な採用は難しいと考える。