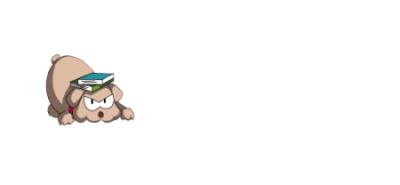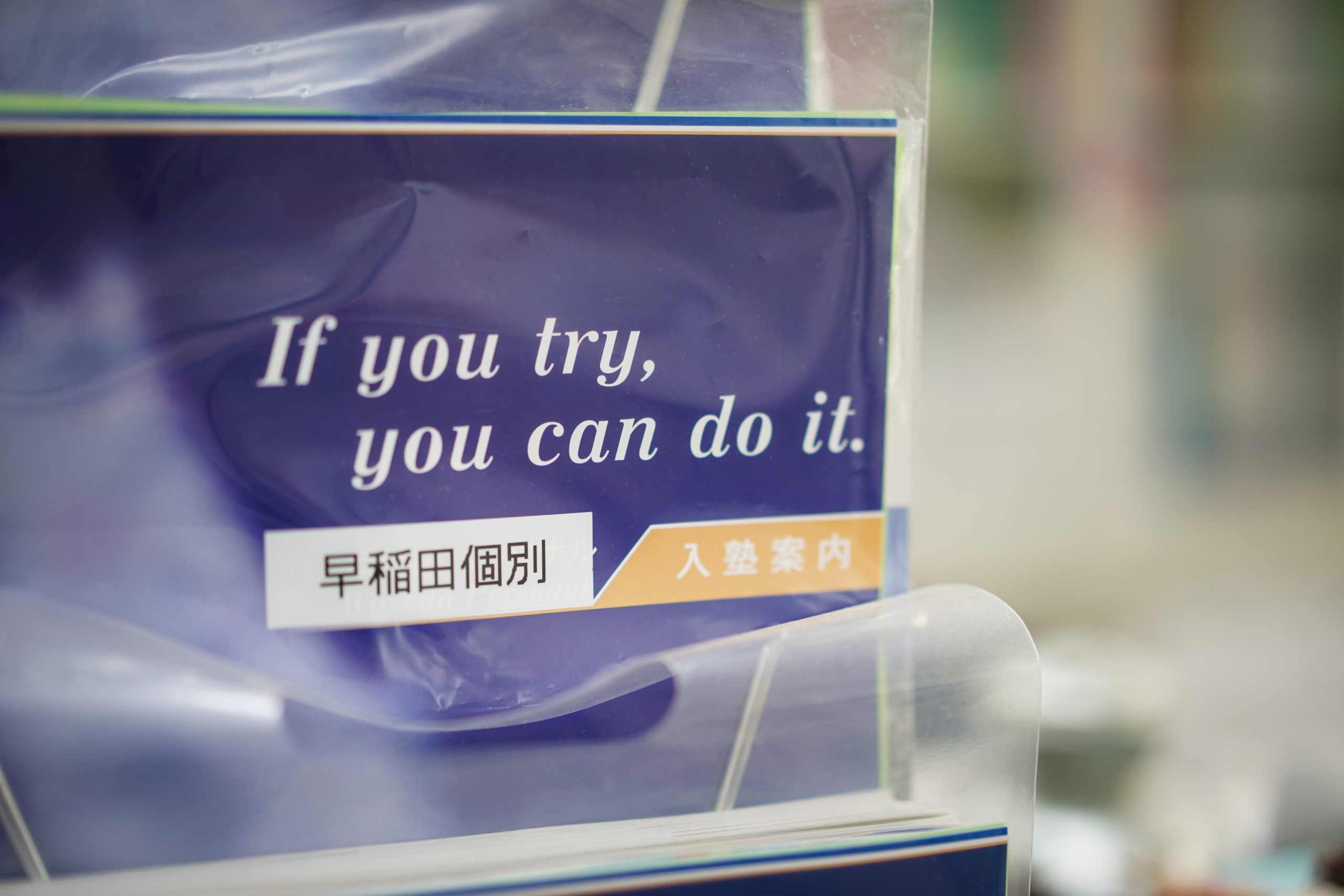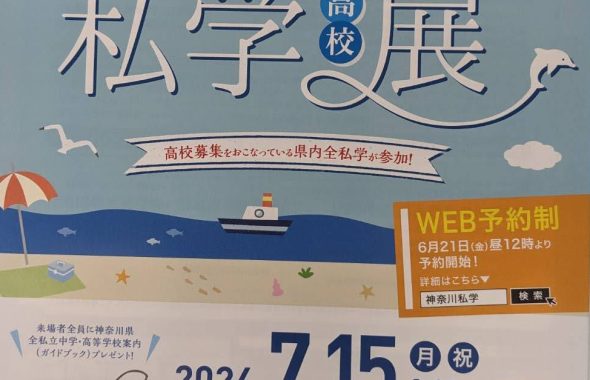年内入試増加加速
年内入試。それは入学前年の秋以降に行われ9月1日以降に出願が開始される総合型選抜試験(旧AO入試)と、11月1日以降に出願が開始される学校推薦型選抜の
総称である。試験の内容は、主に面接と書類審査で意欲や適正などを見て合否が判定されることが多い。このような選抜方法で、2024年度の私立大学の入学者のうち、約6割が年内入試の合格者であった
このような中、多くの私立大学ではこの年内入試に学力試験を課す大学が増えている現状がある。これは文部科学省が条件付きで容認したためで、2025年度では23校が学力試験を課す「年内学力入試」を新たに実施する見通しだ。文部科学省が容認に至るルールでは、学力試験の実施は2月1日からとなっており、年内入試で学力を測る手段としては、小論文や実技検査口頭試問などを示してきた。ただこのルールは有名無実化しており、関西のある私立大学では、年内学力入試が広く行われてきた。昨年度首都圏にある東洋大学が年内学力試験を導入すると、首都圏でも東洋大学を追従する大学の動きが拡張した。このようなことから文部科学省は、昨年12月に学力試験の期日遵守を全国の大学に通知した。一方、志願者の学力を試験で把握したいとの大学側の要望は強く、文部科学省は今年6月、小論文や面接など複数の評価方式を組み合わせることを条件に年内学力試験の容認に転じた。
首都圏の1都3県(神奈川県・千葉県・埼玉県)にある194校のうち、今年度から年内入試を実施するのは、立正大学や拓殖大学など23校になる見通しである。これで昨年度から実施した13校と合わせると37校となり、約2割に当たる大学が年内入試を実施することとなる。
ただ高校側はこの状況を決して喜んでいる訳ではない。このような動きに今後も拍車がかかるとして警戒感があるとしている。本当に早期化は喜ぶべきではないのか。生徒を中心にして考えると、年内に進学先が決まり、安心感が早く持つことで高校生最後を満喫できるであろう。しかし、2月1日以降の試験で進学先を決めたい生徒にとってはどうであろうか。進学先が決まって安心している生徒と、まだ決まってはおらず、これから勉強の最後の追い込みをかけている生徒が一つ教室にいる状況には首をかしげるところがある。また大学の二極化が明確化していくだろう。比較的偏差値が高くない大学が年内入試で生徒を確保する、難関校と言われる大学が2月1日以降の試験で生徒を確保するといった感じであろうか。