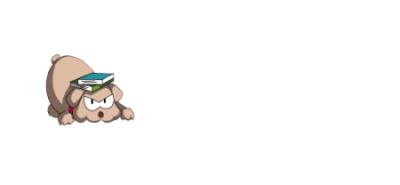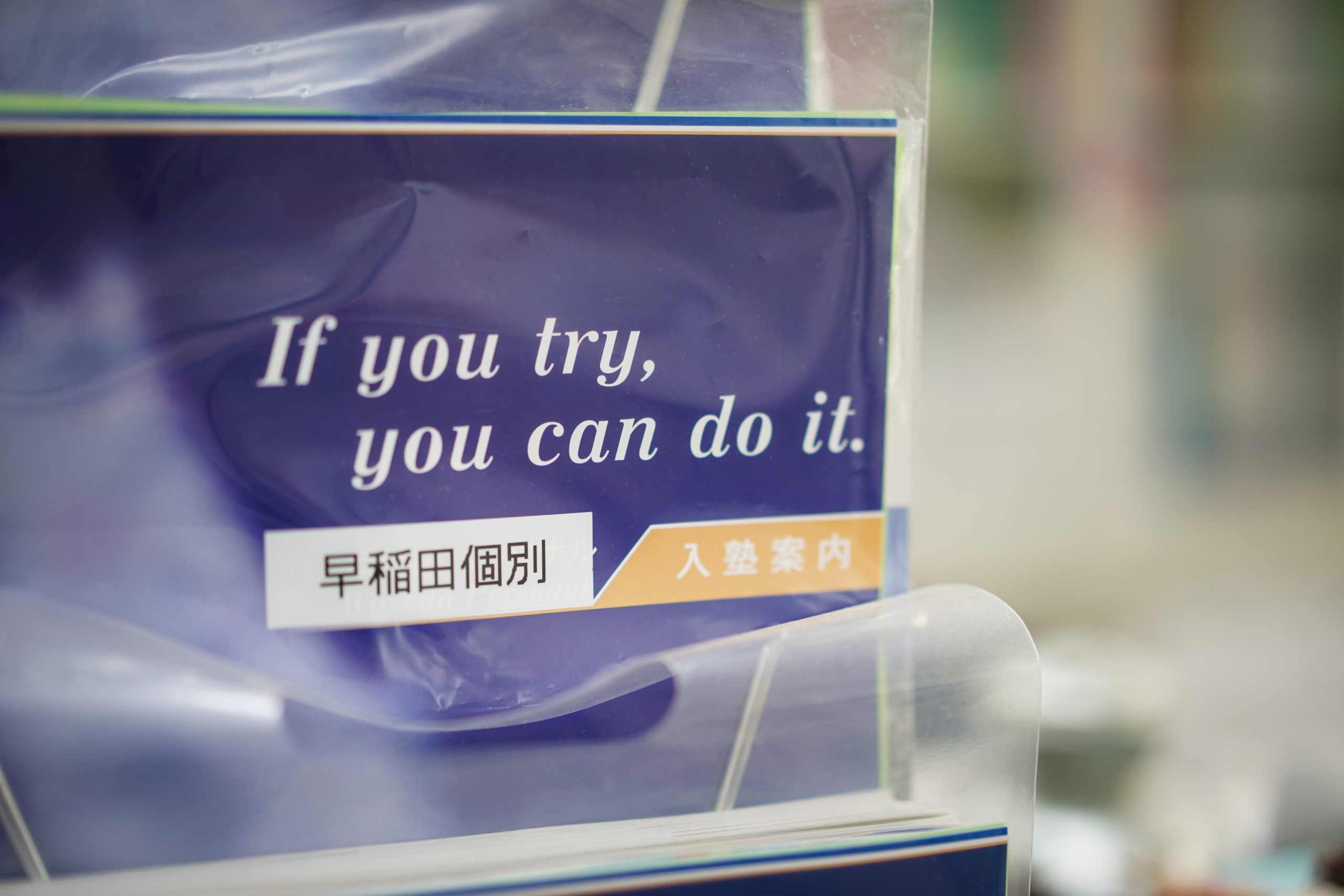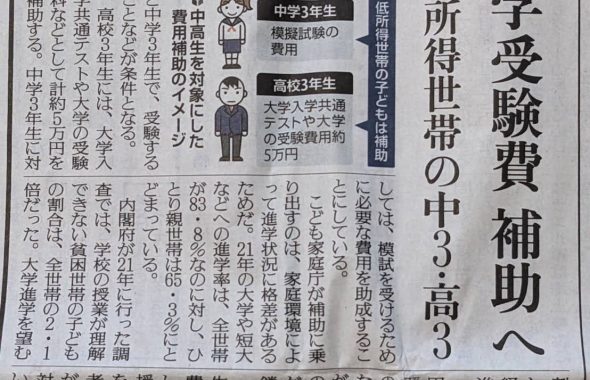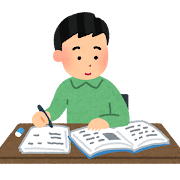
武庫川女子大学共学化へ
兵庫県明石市にある、女子大学として日本最大の学生数を抱える「武庫川女子大学」が2027年度から男女共学となることを発表した。経営面では順調であるが、18歳以下の人口のさらなる減少と女子大学離れへの強い懸念、そして危機感から、あえて先手を打った格好であると言える。全国的に生徒募集に苦戦する女子大の動向に今後どのような影響を及ぼすのか注目をするところでる。
武庫川女子大は1949年に設立開学され、女子大で最多の9,635人(2025年5月1日現在)が在籍しており、建築や経営、社会情報など女子大には珍しい学部の設置で人気を集め、定員充足率は95%と高い数値を収めている。それなのになぜ、という疑問が湧いてくるところであるが、その要因の一端は学部によって大きな定員割れを生じたところにある。特に今年度設置した環境共生学部は、定員120名に対して入学者はわずか34人に留まった。大学関係者は、「これは大きな致命的な失敗である」と語った。この結果、資産運用の観点から収支を見ると黒字ではあるが、授業料収入と教職員などの給与などの支出といった本業で見ると赤字となり、状況は良くないと言える。
こういった話題は、東京にある恵泉女学園大が2024年度から生徒の募集停止したことは記憶に新しいところであり、同年兵庫県にある神戸海星女子大学、2026年度からは京都の名門ノートルダム女子大の募集停止の話題が大きく取り上げられた。また停止ではなく共学化の道を取った大学も少なくない。2023年度には鹿児島純心女子大、2025年度には名古屋女子大、神戸松蔭女子学院大、そして2027年度からは仙台白百合女子大が予定しており、女子大離れという逆風にさらされている。
文部科学省は、全国の大学の約6割が定員割れしており、設定学部が一部に偏っている大学に定員割れの傾向が強いとみている。
共学化において、過去の例を見てみると武蔵野大学や京都橘大学は学生が飛躍的に増えた成功例がある。京都橘大学は、学生数が3.6倍になり、志願者は13.4倍になった。またこれとは逆に失敗した例も少なくはない。神戸山手大学では、共学化にしても定員割れは解消できず、結局他大学に吸収合併されてしまった。
結局、誰もが魅力を感じる学びが提供できるか、これが生徒確保の最大のポイントとなるのではないだろうか。「良妻賢母」とうたった過去の女子大の理念は古く、「キャリア教育」を掲げる女子大のみが生き残れるかもしれない。